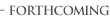|
洋画と手芸
|
| ©Ken Sasaki |
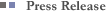
会場:nca | nichido contemporary art
会期:2025年3月21日(金)~ 5月10日(土)
営業時間: 火 – 土 11:00 – 19:00 (日・月・祝 休廊)
オープニングレセプション:3月21日(金)17:00 ~ 19:00
作家:三岸節子 / 佐々木健 / 谷澤紗和子 / ホウ・イーティン / 鴨居羊子 / 宮田明日鹿 / 碓井ゆい
nca | nichido contemporary art は能勢陽子氏キュレーションによるグループ展、「洋画と手芸」を開催いたします。
「洋画」と「手芸」―両者はまるで正反対のようにみえる。近代以降、観ることを目的とした芸術作品としての「絵画」や「彫刻」は男性が手がけるもの、家庭内で行われる編物・刺繍・裁縫などの「手芸」は女性が行う趣味的なものとされていた。昭和初期には、女性が画家、殊に洋画家を志すには、家庭と社会双方からの強い抵抗があった。日本画は子女の嗜みや教養とされたが、「洋画」は男子一生の業とする社会通念があったのだ。女性が入学できる美術学校は1900年創立の女子美術大学のみで、男性と同様に油絵を学ぶには、1945年のGHQ主導による「女子教育刷新要項」の実施を待たねばならなかった。その女子美術大学では、「日本画」、「西洋画」、「彫塑」、「蒔絵」に加えて、「編物」、「造花」、「裁縫」の科目が設けられていた。そして編物や裁縫などの「手芸」は、純粋芸術ではなく、社会的、経済的価値の低いものとして女性に紐づけられ、工芸よりもさらに下位に置かれた。
時が過ぎ、多様な素材や技法を横断する現代の芸術表現をみてみると、刺繍や編み物、アップリケ、切り紙などの「手芸」的要素はそこかしこに見出され、社会から見えなくなっている家庭内の仕事や女性の役割を見事に逆照射している。さらに、ともに集い、語らいながら編んだり縫ったりする行為は、地域のコミュニティ形成やケアとしても機能している。翻って「洋画」に目を向けてみると、日本の近代美術の成立過程そのものといえる言葉とともにすっかり色褪せて、以前の権威や地位を失ってしまったようにみえる。いま、洋画の老舗画廊の現代美術部門であるnca|nichido contemporary artで展覧会をするにあたり、この両極端にあるかにみえる「洋画」と「手芸」を出会わせてみたい。
1928年に創業した日動画廊は、藤田嗣治、岡田三郎助、梅原龍三郎、安井曾太郎などの洋画家に加え、これら男性画家たちに比べれば数は少ないものの、三岸節子、桂ゆき、桜井浜江などの女性画家たちを紹介してきた。三岸節子(1905-1999年)は、当時の例に洩れず父から日本画をするよう窘められたが、洋画家への道を突き進んだ。三岸が戦後、1945年9月にいち早く活動を再開したのも、この日動画廊であった。また、革新的な下着デザイナーとして知られる鴨居羊子(1925-1991年)が1966年に初めて絵画の個展を行ったのも、大阪の日動画廊であった。鴨居は質素で地味な白い下着しかなかった1950年代に、ゆったりとした奇抜な下着の着用による女性精神の解放を謳ったのだった。
そして現代の作家たちは、多様な「手芸」的要素を作品に取り込み、美術のヒエラルキーを解体しながら、私たちの生活に近いところでその成り立ちや意義を問う。画家の佐々木健は、権威の象徴としての絵画の主題にはなりそうもない家庭内で縫われた刺繍や雑巾を、油絵具で丹念に描き出す。谷澤紗和子は、切り紙の技法を用いて、岡田三郎助(1890―1954年)に師事した洋画家・有馬さとえ(1893―1978年)をモチーフに、当時形成された女性像やその背後に隠れた女性洋画家の抑圧と秘めた強さを掬い取る。碓井ゆいは、鴨居羊子の絵とともに、刺繍やアップリケ、パッチワークが縫い込まれた下着やベッドカバーを展示して、女性の身体に生じる微細な変化に、また遠い場所で今も上がる火の手に注意を向ける。台湾出身のホウ・イーティンは、日本統治時代の学校における良妻賢母教育としての裁縫、園芸、体育を、記録写真に施した刺繍により浮かび上がらせる。宮田明日鹿は、手芸を介して人々がともに語らい、それぞれの人生を縫い、編みあげる、寄り合いの場としての「手芸部」を各地で展開している。かつての女性芸術家たちの奮闘と、「手芸的」技法や要素を取り込んだ現代作家たちの作品は、マイナーとされてきたがゆえの奔放さとユーモアとともに、特権的な美術制度や社会に反旗を翻すだろう。
能勢陽子(キュレーター)
碓井ゆい(1980年生まれ/東京都出身、埼玉県在住)
インタビューやリサーチに基づき、刺繍やアップリケ、パッチワークなどの手芸的な手法を用いて、家庭内の労働や女性に対する抑圧を可視化する。本展に吊り下がる下着には、中世ヨーロッパの女性の生理にまつわる迷信が刺繍されている。いわく、「いぬが きょうぼうに なる」、「はなが かれる」、「はんざいを おかす」など。もう一方の下着には、生理になった瞬間の体感が縫い込まれており、表面からはわからない女性の身体の機微が示されている。小さなベッドカバーには、今もガザで上がる火の手が縫い合わされており、それを砲撃のようなステッチが覆う。温かな休息の場であるはずのベッドにおける戦禍は、安寧の場が奪われた遠い国の人々について想いを馳せさせる。
鴨居羊子(1925-1991年/大阪府出身)
白い下着が慎ましく望ましいとされた時代に、女性自身が楽しむカラフルなランジェリーをデザインし、下着界に革命を起こした。下着のデザインのみでなく、画家、人形作家、文筆家として、マルチな活動を展開した。弟は日動画廊を代表する画家の鴨居玲である。正式な美術教育を受けたことのないわゆるセルフトートの画家であり、明るい海や野原で動物や花々に囲まれた女性像を多く描いた。本作でも広がる青い海を前に、愛犬「鼻吉」とともに釣りをしている自身の姿が描かれている。鴨居にとって下着のデザインは社会に対する愉快な挑発であり革命であったが、絵画やオブジェの制作は自らの創造性を純粋に発露させる手段であった。
佐々木健(1976年生まれ/神奈川県出身、東京都在住)
雑巾、テーブルクロス、硬貨など、大文字の絵画の主題になりそうもない身近なものを、油絵具で丹念に、写実的に描き出す。その作品は、普段取り立てて意識を向けることのない対象を通して、家庭内の労働やケアといった問題に焦点を当てる。《祖母のテーブルクロス|ロサ・ユゴニス》(2024年)は、針仕事で家計を支えていた祖母が刺繍したテーブルクロスを、その質感を感じられるほど丹念に描いたものである。また《テーブルクロス(祖母と母と2人の叔母)》(2013年)は、祖母、母、2人の叔母が四辺に刺繍を施したテーブルクロスを、それぞれの手の跡がわかるほど微細に描いたものであり、生活への愛着に満ちた女性たちの共同作業が絵画になっている。
谷澤紗和子(1982年生まれ/大阪府出身、京都府在住)
美術制度の周縁に位置付けられていた切り紙の手法を用いて、近代以降に形作られた女性像や女性芸術家たちの存在をめぐる作品を制作する。その作品は、女性の表現者に与えられた固定観念に疑問を投げかけつつ、彼女たちにオマージュを捧げて現在の地点からの解放を試みる。《水仙》(2024年)と《二つの顔》(2024年)は、女性洋画家の先駆者であった有馬さとえ(1893―1978年)の絵画を基に制作されたものである。谷澤は、現在あまり知られることのない有馬が描いた水仙の枠外に、反抗的に舌を出す球根とそこから力強く伸びる根を加えた。また《二つの顔》では、向き合った二人の女性の肖像画の下部に、球根を介して手を携えそこから根が伸びてゆく様を加えて、女性の連帯を示している。《女性像の演習_O》では、有馬が師事した岡田三郎助(1890-1954年)が美人写真コンテストの広告のために描いた《ダイヤモンドの女》(1908年)をモチーフに、その像が反転して剥がれ落ちた像を加えて、典型的な女性美の形成に疑問を投げかけている。また切り紙をアクリルで挟んだ「矯めを解す」のシリーズでは、社会の固定観念や役割に縛られた女性たちを、女性像や赤子、重機をかき消すように這う線や、「くそやろう」、「うばうな」、「No」という明快に拒否する言葉により、爽快感とともに解放することが試みられている。
HOU I-Ting (1979年生まれ/高雄市[台湾]出身、台北市在住)
女性に紐づけられる裁縫や調理を作品に取り込み、女性の労働環境や学校教育により精神と身体両面に植え付けられるジェンダー規範について問う。1895年から1945年まで日本の植民地とされた台湾では、1872年発布の日本の学制が適応されており、女子に裁縫、機織り、洗濯、料理などを含む「手芸」が教えられていた。本作では、日本統治時代の台湾の学校で行われていた手芸や園芸、体育の授業の様子を写した記録写真の一部に刺繍が施されている。「台湾総督府」の文字の前で刺繍を行う少女たちの中華服は、ホウの刺繍により華やかに浮かび上がる。植民地にされた国は宗主国との関係上フェミナイズされやすいが、そこにおける「良妻賢母」教育は、刺繍により幾重にも重なるジェンダー化を仄めかす。
三岸節子(1905-1999年/愛知県出身)
戦前、戦後を通じて活動した女性画家の代表的な存在である。1921年に洋画を学ぶため上京。本郷洋画研究所で岡田三郎助に師事し、その後女子美術学校(現・女子美術大学)で学ぶ。1924年に洋画家の三岸好太郎と結婚するも、1934年に死別。三人の子を育てながら、画家として生計を立てる決心を固めた。1947年に女流画家協会を結成するも、その後脱退。1968年にフランスに移住し、1989年に帰国する。1994年、女性洋画家として初めて文化功労者になる。女性的な作風を求める当時の社会に抗して、アンリ・マティスやピエール・ボナールなどのフランス絵画の画風を取り入れた。生涯に渡って花を描き続けたが、花は三岸にとって生命エネルギーそのものであった。
宮田明日鹿(1985年生まれ/愛知県出身、三重県在住)
改造した電子編み機や編み物による手芸的手法により、私たちの生活に近いところからそっと社会の問題に触れる作品を制作する。本展に展示されているのは、2023年に保護猫喫茶「necoma」で開かれた《庭のはなし》に出品された作品である。庭で無農薬野菜を育てながら、人間に所有・管理される土地に猫や風が運んでくる種から勝手に育つ植物を眺めるうち、自然と社会における見えない境界やそれを超える可能性について考えるようになった。風にそよぐ編み物や猫のための枕やおもちゃは、人間が定める制度や固定観念を軽やかに揺るがし、越境するものたちの形跡である。また、布の上に束ねた糸を編み込んでいくタフティングの手法を用いた《tata》(タタ)は、2017年から宮田とグラフィックデザイナーの岡田和奈佳の協働により制作されているシリーズである。
自身の制作と並行して展開しているのが、手芸を介して人々が集う「手芸部」の活動である。会場に流れる映像は、宮田が2017年から名古屋市港区で開催している「港まち手芸部」の様子を収めたものである。手芸をしながら互いに語り合い、学び合う手芸部は、「家の中のことを外に出してみる」実践として、各地で継続して行われている。
愛情を込めて作られ、経済的対価を求めることなく、ときにギフトとして親しい人々に贈られる手芸は、経済システムにおける物の価値を改めて考えさせる。同時に、“愛情”や“経済活動の枠外”であることが、女性に望まれ、課されていることにも気づかされる。宮田は画廊で行う本展において、売上の10%と作品価格を超えた分をパレスチナの支援団体に寄付することにしている。それは、美術システムにおける物の価値と価格についての一つの再考でもある。