
|
ピンリン・ホワン
|
| @Pin-ling Huang |
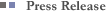
場所:nca | nichido contemporary art
会期:2023年11月22日(水)- 12月23日(土)
営業時間:火 – 土 11:00 – 19:00 (日・月・祝日休廊)
オープニングレセプション:11月22日(水)17:00 – 19:00 *作家が在廊いたします
nca | nichido contemporary artは台湾出身のピンリン・ホワンによる個展「窓外風景」を開催いたします。
ホワンは自身の記憶を辿り、描き留めた何冊ものスケッチブックをもとにして1枚の絵を完成させます。柔らかで透明感のある色彩と、滑らかな筆の痕跡によって独特の世界を創造し、実在しない風景でありながらも、どこか懐かしさと心地よさを感じます。
本展「窓外風景」の作品シリーズでは、SNS上で観た様々な窓越しの風景をモチーフにしています。ホワンが毎日欠かさずに確認するインスタグラムには窓からふりそそぐ光や生き生きとした植物といった、美しい風景が日々更新され、一見ありふれた風景の背後にみえる複雑さに惹きつけられるというホワンは、膨大なイメージ(情報)のなかから、ミクロとマクロの視点を行き来し新しいイメージを構築します。
鏡としての風景画―黃品玲の新作をめぐって
内在化される風景
黃品玲(ピンリン・ホワン)は、台湾を拠点に活動する画家である。2009年に国立台北芸術大学を卒業後、2011年からパリに渡り、2014年にエコールデボザール(フランス国立高等美術学校)大学院を修了した。2022年から2023年にかけて、横浜の黄金町エリアマネジメントセンターのアーティスト・イン・レジデンスのプログラムに参加している。
ここでは、横浜のスタジオで制作中の新作を手掛かりに黃の作品について考えてみたい。と言うよりも、これを手掛かりにするしかないと、言うべきだろう。黃のホームページには、確かに過去の作品が紹介されているが、実作でないので、マチエールなど実見で得られる情報がないからだ。と言うことで、今回は、限られた情報から幾つか黃の作品を考える上で重要と思われる点を考察したい。
さて、制作中の十数点の作品には、大きく二つのスタイルを見出せた。一つは、細かい筆致で塗り重ねられた抽象的というよりは具体的な風景を想起させるイメージ、今一つは、それよりは大きなストロークで流れのような抽象的とでも言うべきイメージである。こうした違いがあるものの、どちらも緑色と諧調のある青色が多用されている点は共通している。つまり、自然=風景がその底流には流れているように思えた。
実際に、黃から話を聞くと、細かい筆致の方は、窓越しの風景、ただし、ここでは現実の風景でなく、SNSで検索し見つけ出したイメージが素材として使われている。そして、もう一つは、自身のこれまでの様々な場で視覚も含め五覚によって得られた風景の記憶の総体がその素材の源泉となっている。
ところで、窓越し、あるいは窓の先の世界=風景については、15世紀、一点透視図法を体系化したレオン・バッティスタ・アルベルティの『絵画論』をあげることが出来、そこでは、絵画のキャンバスを窓枠になぞらえ、その作図法が示された。いわゆる絵画の透明性に繋がる理論だが、まさに黃の場合文字通り透明なガラスの窓越しから伺える風景が想定される。とはいえ、ここでの窓越しの風景に見られる透明性は、実の透明性というよりは、建築史家で建築家のコーリン・ロウ(Colin Rowe)が画家、建築理論家のロバート・スラツキー(Robert Slutsky)と1963年に発表した論文「透明性 実と虚」で指摘した現象としての「虛」の透明性(フェノメナル)と言うべきかもしれない。それは、ここでは、何よりもブラウザを通して得られたSNS上のイメージであり、そもそもこれ自体が、リアルなイメージではないからだ。アルベルティの15世紀における建築の窓は、今日のような透明性の高いガラス越しではなく、まさに外界そのものを開け放たれた窓からの直接の眺めと言うべきだろう。一方、今日では、視覚情報こそ人間の網膜を通すことに変わりはないとは言え、その対象は、現実世界以上に、デジタル処理された無数の視覚的イメージに包囲されている。まさに、虚の透明性である。
ところで、黃は、普段ノートに、まるで日記のようにテキストやイメージを書き残している。それは、スケッチのようでもあり、ドローイングのようでもあるが、黃の思考のメモとでも言うべきものである。画家にもよるが、完成された作品とそこに至るプロセスとしてデッサンやドローイングを同時に発表する場合もあれば、黃のように、思考のプロセスはあくまでプロセスとして完成された作品の常に背後に置かれる場合もある。さらに言えば、完成へのプロセスという言い方は、実は当てはまらず、黃のこれまで経験した記憶はいつも行きつ戻りつし、あるいは書き替えられ、完成のための素材というよりは、形に出来ない記憶のカオスとして存在しているのではないかと思われる。
黃の経歴を見ると、冒頭に記したように、ヨーロッパ、この場合パリや、そして南仏にも滞在した経験を持っている。まるでかつての北ヨーロッパの画家たちが経験したような、決定的に異なる南仏の光のあり方を黃も別の形で経験している。また、黃の作品に寄せた台湾のインディペンデント・キュレーターで美術批評家Li-Hao Chongのエッセイ「A Brushstroke, a Poetic Floating」によれば、黃は、画家としての制作の積み重ねと同時に、夥しい種類と数の文献(専門書のみならず広く文学作品も含め)を渉猟していることが分かる。テキストから浮上するある種の視覚的なイメージを求めてそうしたテキストを読破するのではなく、黃が抱える闇や混沌から誘引されるテーマに従って、それこそ黃を支える物語を獲得しようとする行為だろう。こうした黃の姿勢は、先述したメモにも当て嵌まり、そこでは、完結や完成をそこで目指すのではなく、自らの制作や思考の迷いを迷いのまま保留することを行なっている。
最後に黃の作品は、広い意味での風景画と捉える事が出来るかもしれない。広い意味と言ったのは、風景画の歴史的な変遷を見返したときに、現前の風景を再現するような意味からは、大きく飛躍していると思われるからだ。とりわけ、ヨーロッパでは、近代以前の絵画的主題のヒエラルキーの頂点にあったのは、歴史画=物語画であり、風景画は、いわばその主題(エルゴ)に対する付随的な絵画(パレルゴン)に過ぎない位置付けだった。ここで、詳細に論じる余裕はないが、17世紀辺りから、付随的絵画が、一つの分野として自立しはじめ、現代においては、風景の再現表象から、表現者の内面を映し出す、あるいは、表現者が重ねる対話のためのメディウムとしても機能している。実際のところ、人々が日常生活で感じる風景への憧憬は、何か具体的な素材(木々であったり、山であったり)ではなく、佇んだ場の空気感そのものである場合が多い。風景に対する一定の角度、その日の光の有り様といったものが相対として知覚された時に感じる「何ものか」に心惹かれるのだ。
そして、黃の場合、現前の世界は、心地よいものであったり、時として、見知らぬ不安の表象として刻印される。それは、黃の自身に対する絶え間ない問いかけが制作の過程として繰り返され、表現の方法を変化させる。だからこそ、その作品に豊かな表情を宿らせることになっているのではないだろうか。
天野太郎
東京オペラシティアートギャラリー
チーフ・キュレーター

