
|
劉致宏(リュウ・ジーホン)「パリュウド」2018 3.2 - 4.7オープニングレセプション |
| ©Chih-Hung Liu |
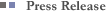
場所:nca | nichido contemporary art
会期:2018年3月2日(金)- 4月7日(土)
営業時間:火 – 土 11:00 – 19:00 (日・月・祝 休廊)
レセプション:3月2日(金)18:00 – 20:00 (作家も来日致します)
nca | nichido contemporary artは台湾出身の若手アーティスト、リュウ・ジーホン(劉致宏) による個展「パリュウド」を開催いたします。リュウは日常生活や周囲の環境、また旅先で見た風景や事象を多面的に捉え、独自の詩的感覚を織り交ぜながら物語を紡ぐように作品に表します。絵画に表れる力強く流れるような筆致は視点によって姿を変え、存在感をもって目の前に大きく迫ります。表現は絵画にとどまらず、インスタレーションや、映像、文字、立体など、テーマごとに様々な素材を用います。本シリーズはリュウのスタジオからほど近い陽明山(台北郊外に位置する山)、またその道中でのスケッチが作品制作のもととなっています。
本展はリュウにとって日本初の個展となり、大作含む最新作のペインティング約25点とセラミックの彫刻作品を発表いたします。
流れ動く映像を写生する:劉致宏の絵画創作
「気が滅入って、何かから逃げ出したい時、僕は陽明山までバイクでひとっ走りする。山を越えて、そのまま北海岸まで飛ばしてしまうこともしばしば。」
作家の劉致宏(リュウ・ジーホン)は記憶をもって、道沿いに続く風景の断片を記録することを得意としている。時に、一部想像を織り交ぜたこれらの断片は、現実なのか虚構なのか見分けがつかなくなってくる。このような特殊な「野外写生」は、彼の絵画を通じて、素早く流れ動く光と影、風景と時間をも呈している。劉の作品は、瞬時に描きあげられた写生であり、特異な風格をもつ絵画であり、さらに言えば記憶の再現あるいはその組み換えによる映像でもある。
友人という身分であれ、または仕事上の繋がりであろうと、私は彼と接触するたび、表面的には明るく立ち振る舞いながらも、劉の胸中に渦巻いている、晦渋でいて鋭敏な“語り欲”があることに気づく。多くの物語を他者と分かち合いたいであろう少年のような彼に対し、現存のメディウムは劉自身が語りたいスピードに追いつけていないようだ。あるいは、心に秘めている物語が持ちうる豊かなパースペクティブは、単一のメディウムだけでは完璧に表せないのかもしれない。このような作家の特性と気質は、静態的な絵画といった創作だけに表現されているのではなく、どちらかといえば彼は時をかける美術家のようにも思える。なぜならばストーリーテリングを展開するには、ビジュアルのほか、サウンドやパフォーマンス、そして自らの情動を必要不可欠としているからだ。彼がすでに6冊の『声音地誌(Sound Geography)』を手がけていることからみても、創作概念の延長上にある何かを作家の拘りとして持っていることが窺える。『声音地誌』は、劉の海外のアーティスト・イン・レジデンスにおける成果や、台湾島内でのリサーチ結果を網羅しているほか、物語やサウンドにおける叙述、情緒的でいて時に表現主義たる色彩を充分にまとった写真、写生なども丁寧に盛り込まれている。
『声音地誌』は作家個人の紀行文であると同時に、彼がアートを一つの方法論として、その地域を探査する、または一人の美術家が感知したものを投影する「地誌学」そのものである。観者が作家の文字、描写、映像ドキュメントに沿って、飛躍するイマジネーションを掻き立てる時、時間と空間をもってつくりあげた、流動的な構造へと導かれていく。『声音地誌』がみせる表現とは、作家が意図して仕立てた絵画以外の創作スタイルの結果ではなく、むしろ絵画と一体となった共同体ともいえる。そのどちらも、劉が写生をもって編み出した“流動する映像”の中にある。
「写生」とは本来、東アジアにおける古典絵画の伝統の中では、画家が自然景観や事物を観察し、写しとるといった創作の様式を指すが、近代化が進むにつれて西洋美術の概念が取り入れられるようになり、複数の定義をもつ写生も、実物や風景の観察と同時に描いていく、すなわち西洋絵画の「スケッチ」をも意味するようになっていく。日本の統治下にあった台湾は、直接印象派ならびにポスト印象派のスタイルや技法から入ることで、西洋美術たるものと接触していった。よって、台湾の基礎美術教育の一環である「写生」は、これまでずっと「風景の描写をする」といった振る舞いと緊密に結びついてきた。例えば、台湾に生きる私たちが、誰々さんが「写生」に出かけたと言及した時に、まず多くの人々の脳裏に浮かび上がる情景とは、「よく晴れた朝に、持ち運びに便利な絵筆やパレットといった道具一式をもって、山林や渓谷まで分け入っていく」といったものではないだろうか。
1990年代以降の、台湾における現代美術の発展においては、美術史が受け継いできた伝統と対峙しながらも、それらを振り払うための努力と、革新的芸術の形式もしくは概念を提起するための多くの試みがなされてきた。しかし、たとえこのような新しい流れやシステムの中で創作訓練を受けた若い現代美術作家でも、「写生」の影響をまったく受けずにきたとは言いきれないだろう。時間性とともに、たえず切り貼りされていくディジタル映像の時代に晒されながら、私たちもまたどのようにしてメディアアートにおけるトレーニングの洗礼を受けた今の現代美術作家たちと、「写生」について語り合えるのだろうか? そのような中で、作品を通して、双方のバランスと相補的な関係に対し、すでに作家として見出した答えが劉にはあるようだ。
台湾に根差した言語空間において、「写生」は必ずしも描写、観察、もしくは絵画を仕上げるための技術だけを意味していない。台湾における「写生」の礎を築いた石川欽一郎を筆頭に、かねてより「写生」の語意とその実践は、緊密に自然主義と繋がり合ってきた。よって、私たちが劉の作品にある「写生性」に言及した時、決してただテクニックの運用について討議しているのではなく、それと同時に内側から放たれる強烈な自然主義的な情緒を通じて、創作への理解を深めているのである。劉のこれまでの作品を振り返ってみても、ビデオ映像やインスタレーションであれ、もっとも制作の本質に迫る絵画であれ、どの作品からも作家が動植物または山林に対して抱いている親密さを感じ取ることができる。作家もまた自然への親近感と奥なる情感を、程よい塩梅で創作表現へと転換しているのだ。
もし内に秘めた感受性たるものが、多面的かつ複雑な感情の流動によって構成されていることを考慮するならば、劉がもっとも得意とする叙述的モンタージュという手法こそ、彼の作品を理解する上で、極めて重要なポイントとなるだろう。私は観者として劉の作品(絵画または他の形式による創作)に触れるたび、流れ動く映像をみているような錯覚を覚える。それは、時間軸があるかもしれない映像の間を往来あるいは徘徊しながらも、叙述性の外に存在するポエジーを追っているような感覚である。劉の作品群そのものが、まさに作家本人から送られてくる一つまたひとつの誘いのようであり、観者は彼が旅路で捉えた映像の断片を目の前にして、劉とそれを共にしている感覚を覚えるだろう。作家自身にとっても、遠い異国のレジデンスで作品を生み出すことが旅なのでは決してなく、彼がバイクに乗って近郊の山林に分け入り、目的もなく漫遊すること自体が旅なのである。それは自由を追い求めているある種の渇望であり、世俗に染まりたくない、そこから逃げ去りたい劉の強い気持ちの表れである。だからこそ、自然主義的な狂想ともいえる境地に到達するために、彼は精神の旅へと出かけるのだろう。
狂おしさと躍動を掻き立てるタッチは、劉が鋭敏に捕えた記憶という映像に、強烈な命の鼓動を打ち付け、そしてこの生き生きとしたエネルギーは、作家がつぶさに観察した自然や事物に、高速道路を駆け抜けるようなスピード感を付与している。劉が描く「モンタージュ的な写生」は、異なる3つの速度を同時に提示していることが分かる。その1つに:バイクに乗った時にみた、あのスピード感とも似ている、作家による主観的眼差しがあげられる。これは私的見解に基づく激しい「物理的速度」に対する感覚でもある。2つ目に:記憶の中の映像を辿り、またそれらを切り貼りし、重ね合わせながらナラティブを紡いでいくための時間軸があるということ。これは極めてセンチメンタルな叙述的時間であり、一種の「心像を表象する速度」でもあり、それは観者が空間に抱く想像力をも引き出してくれる。最後に:描かれる対象から滲み出る、ある種の時の流れがみてとれる。盆栽にせよ、道端に居座る犬や森林を構成する植物にせよ、動植物自身が持つ時間というエネルギーが、外在的時間を形成している。私たちはこれを、山野の中に現存する「自然の速度」と呼ぶことができるだろう。このような異なる時間と速度による構造を行き来しながら観賞するという経験は、作家の感情世界を表現として呈しているだけでなく、劉が長きにわたって「地誌学」的論法を用いてきたことにも回帰する。
このたび開催される劉致宏の個展は、アンドレ・ジイドの作品『パリュウド』(Paludes,1895,フランス語で「沼地」という意味)の書名を、展覧会のタイトルとしてそのまま引用している。日記帳のような自伝的小説ともいえる『パリュウド』では、当時パリに住むインテリ階級の間で持てはやされていたシニシズムを風刺した内容が描かれているほか、作者個人の強い孤独感もあぶり出されている。ある種抗うことのできない圧迫感と都市の隙間に身を潜めて生きるしかなかった時代の情況からして、ジイド自身が置かれている場から逃げ出し、自由への渇望に目覚めていったに違いない。またこの想いこそ、劉の個展にも通じる軸となっている。本展の作品群は、作家がみせる映像日記にとどまらず、同時に自己の存在意識と精神状態を伝えるためのインターフェイスである。
あえて結論づけるならば、劉の絵画には時間、空間と記憶に対する鋭敏な観察が充分に反映されており、彼の作品は記憶の旅が織りなすモンタージュであるだけでなく、潜在的な自然主義者が奏でる田園詩でもある。豊かな感性が備わっていると同時に、身近な人や自然にも目を向ける作家は、台湾の現代美術界を見渡しても希少な存在である。また、劉がつくり出す芸術空間は、台北市郊外に位置する陽明山と似ている。なぜならば、窮屈な都会の生活に嫌気がさした市民たちが、しばしエスケープできる、探索をする中で記憶を拾い上げることが叶う、いわばひらかれた自然な空間と重なるからだ。私たちの断片的記憶が編み直されるそのプロセスを通じて、豊かな感性によるかけがえのない世界を、己を癒しながらも一歩ずつ再構築していけるのだと、劉は幾度となく示してくれるだろう。
高森信男(国立台北芸術大学関渡美術館キュレーター)
訳:池田リリィ茜藍
劉致宏 | リュウ・ジーホン
1985年台湾・新竹市生まれ。現在台北市在住。
2012国立台北芸術大学卒業 大学院卒業
個展:“NOVEMBER,Hsin-An”‧HOWL Space‧T、台南(2016)、“L’OISEAU BLEU”‧Galleria.H、台北(2016)、“SUMMER FLOWERS”‧Taipei Artist Village、台北(2016)、”SHORT FICTION” 台北市美術館、台北(2014)、グループ展:“Small scenes.”‧nichido contemporary art、東京(2017)、“Harper's Bazaar 15O Years: the Greatest Moments” Taipei 1O1 Mall、台北(2017)、“Very Period”‧VT Art Salon、台北(2017)、 “LADY DIOR AS SEEN BY”‧Christian Dior Foundation、台北(2017)、“A Journey Far From Home”‧galerie nichido、台北(2017)、“An Ode to Thirty”‧Eslite Gallery、台北(2017)、“Media Archaeology: Indescribable Mark of Life” Art Museum NTUA、台北(2017)、“Made In Taoyuan”‧House Art‧桃園(2017)、“TAIPEI ARTS AWARD 2016”台北市美術館,台北(2016)、“TAIPEI BIENNIAL 2016” 台北市美術館、台北(2016)、“2016 On-Site Art Festival-International Art Space” 秋吉台芸術村、山口(2016)、“As Small as the Universe”‧galerie nichido Taipei、台北(2016)、“Playlist”‧VT Art Salon、台北 (2016)、“Changwon Asia Art Festival 2016 – Hide & Seek/Two Jobs” Changwon City Art Hall、釜山(2016)、“Residency Artist II”‧Ilju & Seonhwa Foundation、ソウル(2015)、“trans_2014-2015 : The Features of The Land” 秋吉台芸術村、山口(2015)
レジデンスプログラム:ARTSPACE,シドニー、(2016)Changwon Art Hall、釜山(2016)、Pier-2 Art Center、高雄(2016)、秋吉台国際芸術村(2015)、Seoul Art Space _ Geumcheon、ソウル(2014)、Haslla Art Center、ソウル(2013)

